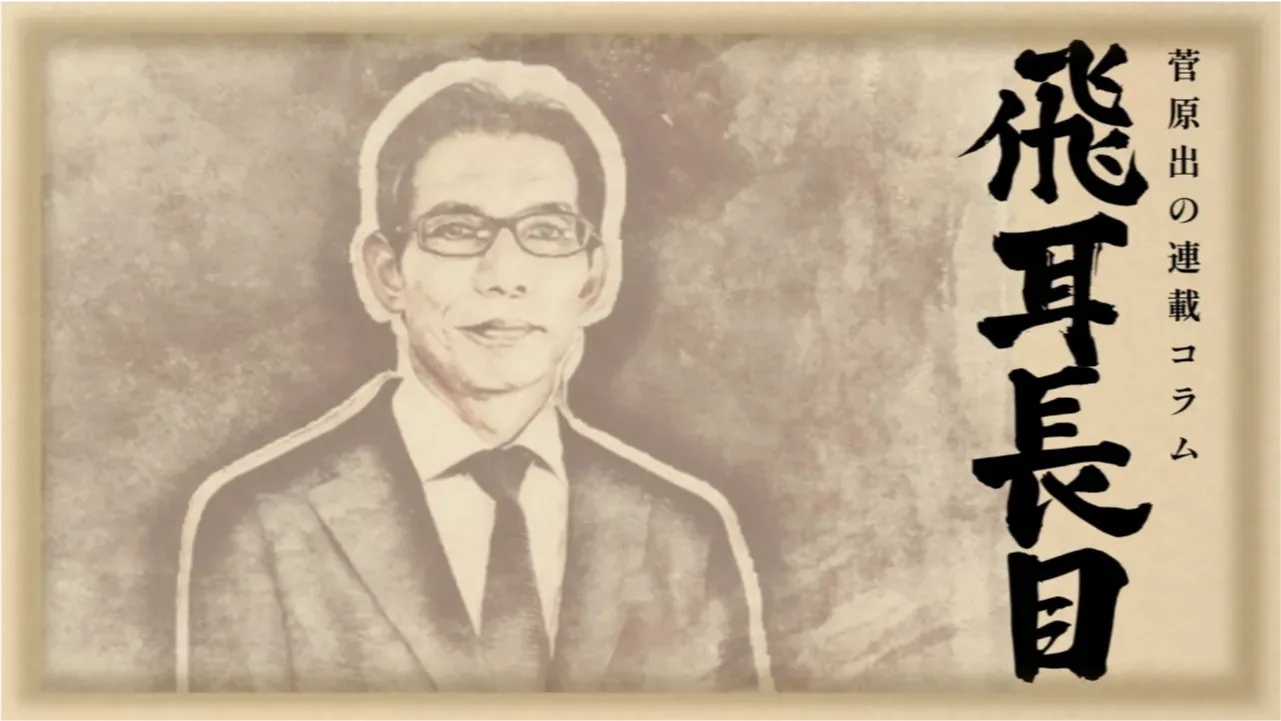トランプ政権の「モンロー主義2.0」
Jan 31, 2025
こんにちは。オンラインアカデミーOASIS学校長の菅原出です。
1.トランプがパナマ運河の返還を求める理由
トランプ大統領がパナマ運河の返還を要求したり、グリーンランド獲得に向けた発言を繰り返していることについて、トランプ政権高官からは「モンロー主義2.0」という言葉が飛び出しています。こうした発言はいったい何を意味しているのでしょうか?
パナマ運河をめぐっては、米国は20世紀初頭に建設を引き受けた後、1970年代に条約を通じてパナマに支配権を譲渡しています。しかしトランプ大統領は、もし「ぼったくり」が止まらなければ、運河を米国に返還するよう要求する、などと主張しています。
パナマ運河の施設は、香港の巨大港湾運営会社ハチソン・ワンポアによって運営されており、このことがトランプ政権の懸念の中心のようです。パナマ運河の入口コロン港は中国のランドブリッジ・グループにより買収され、コンテナの積み下ろし施設の整備が進んでいることも伝えられています。
トランプ政権は、過去30年間に同運河周辺に建設された中国のインフラを国家安全保障上の脅威と見なしているようです。
「中国がパナマ運河を運営しているが、我々はそれを中国に与えたわけではない」とトランプ氏は就任演説で述べています。1977年の条約によりパナマに運河の管理権が委ねられたことを指して、「我々はパナマに与えたのだ。そして、我々はそれを取り戻すのだ」と主張しているのです。
実は米国内でこのような主張をしているのは、トランプ氏だけではありません。米共和党は、「ジミー・カーター大統領が1977年の条約で戦略的資産を手放した」としてかねてから批判していました。ハチソンが港の管理権を取得した際にも、当時のレーガン政権の国防長官キャスパー・ワインバーガー氏は、中国が「極めて重要な情報収集の足場」を得る可能性があると懸念を表明したことがあります。結局、当時の国防総省は、「ハチソンの運用は安全保障上の脅威とは考えていない」と結論づけていましたが。
2023年には、当時、米南方軍司令官だったローラ・リチャードソン将軍が、「パナマ運河沿いに軍事利用に転用可能な施設を持つ中国国営企業が5社ある」と発言して中国に対する警戒感を示したことがあります。中国の国家安全保障法は、同国の民間企業や個人に対して国策への協力を義務付けることができるとされています。このため、ワシントンではトランプ氏以外にも多くの人々がこうした懸念を示してきたのです。
世界貿易の約4%がこの運河を通過しており、そのうち70%以上が米国向け、もしくは米国から外国に向かうものです。米国の石油タンカーやガスタンカーは燃料を太平洋に運び、ペルーのアスパラガス、チリのワイン、エクアドルのバナナを積んだ船が同運河を通って米国東海岸に向かって航行しています。
米国は依然としてパナマの最大の投資国であり貿易相手国です。パナマ運河のデータによると、中国からの貨物は米国に大きく差をつけられ、同運河を通過する貨物の22%にも満たないとのことです。パナマ政府によると、2023年の米国のパナマへの投資額は130億ドル近くに上り、中国の5億1500万ドルを大きく上回っています。中国の軍艦が同運河を通過したのは、ほぼ10年も前のことですから、トランプ氏たちの懸念は過剰だとする主張もあります。
ただ、米国の「裏庭」に中国のインフラが整備されていくことを、共和党はもう我慢できないのかもしれません。パナマは米国と緊密な関係にあるがゆえに、トランプ大統領の圧力には非常に弱い立場にあります。米国は過去にも同国に軍事的に介入しており、例えば1989年には米軍をパナマに侵攻させ、当時の独裁者マヌエル・ノリエガを打倒してしまったことがあります。
今後、トランプ政権がどこまでパナマに対する圧力を強めていくのか、注意深くみていきたいと思います。
2.トランプ政権がグリーンランドにこだわるのはなぜか?
続いて、グリーンランドについても見ていきましょう。トランプ氏は、米国によるグリーンランドの所有が「絶対に必要」だと主張。1月7日の記者会見でグリーンランドやパナマ運河の取得に向け「軍事的もしくは経済的強制力」の行使を排除する意向かどうか問われると、これを否定。「どちらについても保証はできない。ただこれだけは言える。我が国は経済安全保障の観点からそれらを必要としている」とぶっきらぼうに答えていました。
トランプ氏がグリーンランドにこだわる背景には、北極海航路をめぐる米中の戦略的競争があるようです。
中国は近年、グリーンランドでの採掘事業への投資など、この地域における経済的プレゼンスを高めてきました。中国はこの島の戦略的に重要なプロジェクトへの投資を続けており、2018年には、中国が同島の3つの空港に資金提供することを、米国防総省が介入して阻止したこともありました。
中国は、グリーンランドが北極海のすべての航路に位置していることから、特に強い関心を示しているとされています。北京の「氷上シルクロード」構想では、スエズ運河やマラッカ海峡といった海上の狭隘地帯を避け、北極海経由でより短い距離で商品を輸送することを想定しています。
しかし、より重要なのは軍事的な側面かもしれません。グリーンランドは「GIUKギャップ」と呼ばれる、グリーンランド、アイスランド、英国間の重要な海上交通路の一部であり、冷戦時代にはこの海域がソ連の潜水艦が大西洋に出ようとする際の唯一の出口であったため、ここを封鎖することが当時の米海軍の主要な任務の1つでした。要するにここは軍事的な要衝なのです。
参考:政策シンクタンクPHP総研 Voice 地政学的要衝研究会『「大人の海」としての北極海』石原敬浩(海上自衛隊幹部学校教官、慶應義塾大学非常勤講師、二等海佐)
米国はすでに、かつての「スール空軍基地」として知られる、同国最北の基地である「ピツフィク宇宙基地」を同島に有しています。この基地には、米国の弾道ミサイル早期警戒システムの一部であるレーダー基地が含まれています。
近年、ロシアは同海域での潜水艦パトロールと演習を強化していますが、ウクライナ戦争以降、中国の「ジュニアパートナー」化したロシアは、この海域に中国を引き入れるようになっているのです。
最近中国の海警局は、北太平洋でロシア国境警備隊と合同の訓練やパトロールを開始しています。中国にとってこの合同訓練やパトロールは、北極海の開発を進めるうえでも重要だと考えられています。北太平洋でロシアの海上警備当局との連携を深め、同国の補給拠点などを活用できるようになれば、中国船の航行範囲が広がり、北極海に進出しやすくなります。
中国はすでにアイスランドにオーロラ観測施設を建設したり、グリーンランドにも人工衛星の地上局を建設するなど、この地域への影響力を拡大させています。米国が遅ればせながらグリーンランドへの影響力を確保することで、中国の軍事的プレゼンスが近くまで及ぶことを許さない、そうした米国側の意志の表れが、トランプ氏の「グリーンランド購入」発言の背後にあるのだと考えられます。
3.ウォルツ大統領補佐官の分かりやすい説明
トランプ政権の国家安全保障問題担当大統領補佐官であるマイク・ウォルツ氏は最近、「メキシコの麻薬カルテルへの対処」、「パナマ運河の支配権掌握」、「グリーンランドの獲得」、「アメリカ湾の名称変更」を、トランプ政権の「モンロー主義2.0」と呼んで話題になりました。
「これはグリーンランドだけの問題ではなく、北極圏の問題だ。ロシアは60隻以上の砕氷船を保有し、そのうちのいくつかは原子力砕氷船だ。我々は砕氷船を2隻しか保有しておらず、そのうちの1隻が今まさに火災を起こしている。これは重要な鉱物資源の問題でもある。これは天然資源の問題なのだ。これは、北極の氷が後退するにつれ、中国が今、砕氷船を大量に建造し、同様に進出していることについての問題である。つまり、石油とガス、そして我が国の国家安全保障、そして重要な鉱物資源がかかった問題なのだ」と説明しています。
さらに、「すでに北西航路を通る船舶航路が使われ出しており、ここの安全保障を確保しなければならない。今、我々はアラスカ北部に1つも基地を持っていない。カナダにもっと頑張ってもらう必要があるのだが、カナダはNATOの防衛支出で最下位に次ぐ順位だ」と述べたうえで、
「これは西半球における米国のプレゼンスの再確認の問題である。麻薬カルテルに対処することであれ、パナマ運河、グリーンランド、そして『アメリカ湾』の呼び方も含めて、モンロー主義2.0と呼んでもいい。これはすべてアメリカ・ファースト主義の一部であり、これまであまりにも長い間無視されてきた問題に我々が取り掛かるということだ」とウォルツ氏は解説しました。
なんとも分かりやすいご説明です。つまり、パナマ運河についてもグリーンランド獲得についても、トランプ大統領がその場の思い付きで発言しているわけではないということです。トランプ政権がこのような認識の下で、堂々と「モンロー主義2.0」を掲げて外交を進めていることを、私たちも深刻に受け止めなければいけませんね。
もう国際秩序や国際ルールは我々を守ってくれません。具体的な力を持たなければ、自国の利益を守ることはできない、そういう時代に突入していることを認識する必要があります。
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
世界は、まさに100年に一度の大きな変動期を迎えています。歴史や地政学をはじめ、国際政治や安全保障を学ぶことがますます重要な時代になっていることを、日々実感しています。
1月20日には宮内雄史先生の新シリーズ「中国の経済・社会インフラ」の第2弾、27日には第3弾が公開されました。最近中国のAI企業DeepSeekが世界を驚愕させましたが、こうした企業が現れても私はまったく驚きませんでした。宮内先生の動画を観て中国経済の恐るべきポテンシャルを知っていたからです。今こそ宮内先生の講義は必見です。是非ご視聴ください。
今年もOASISを通じて皆様とたくさんの学びを共有したいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。
菅原 出
OASIS学校長(President)